
Storyteller – 識る単位
2012年 11月3日(土・祝)~12月16日(日) 10:00 - 18:00/無料
青山悟
AOYAMA Satoru

《Light and Patterns》
創造の所在
近藤由紀
青山悟は一貫してミシン刺繍による作品を発表している。新聞や雑誌の記事(fig.1)、自身のスタジオ(fig.2)や風景写真(fig.3)といった既成の、どちらかといえばありふれたイメージをモチーフとして転写し、ミシン刺繍によって再現する。その表面は精巧を極め、ほとんど完璧な刺繍によるコピーであり、一見絵画的ですらある。だが青山はミシン刺繍によって絵画的イメージを再現しながら、そうしてできたイメージといわゆる「絵画」とをはっきりと自覚的に区別する。それは青山がテキスタイルという分野に主軸をおいていることに対する意識とその自負によるといえる。
青山は作品や活動について語る時、しばしばアンディ・ウォーホルを引き合いに出し、自らも「ポップアーティスト」を標榜する。当然それは50、60年代のそれと同じ意味をもつのではないく、テキスタイルの文脈における「大衆文化に基づく芸術作品」ということが意識されているといえるだろう。熟練の技による精巧なミシン刺繍にも関わらず、青山がしばしばその作品を「誰にでもできる方法で」[1] と語る時、それは芸術作品とは天賦の才が与えられた芸術家の手によってのみ生まれるという考え方に対抗する立場の表明となる。青山の作品においては、絵画や彫刻といったいわゆる「ファイン・アート」におけるオリジナリティの問題や作品に現れる作者の身体性といった、ある種個に属する部分は徹底して排除され、アプロプリエートされたイメージは、機械であるミシンと同化したような青山の技術を通し、テキスタイルの作品として複製される。ウォーホルは「機械になりたい」という有名な言葉を残したが、青山はむしろイメージを量産する機械となるのではなく、一つの媒体なりイメージをテキスタイル化することで変質させる。
この青山の媒体性は、青山の作品が、常に社会と強く関与しようとしていることとも無関係ではないだろう。刺繍によって再現されたイメージは、ほとんどの場合作者の外にある。青山は抽出されたある場面や出来事に対する姿勢を声高に主張するというよりは、現代社会に氾濫するイメージを受け取り、それをミシン刺繍によってアプロプリエートし、提示し続ける。それは雑誌や新聞等の社会的/政治的イメージのランダムな使用のみならず、典型的とも思える風景写真や肖像写真のイメージを用いたシリーズや、祖父の絵画と関連付けられたシリーズにも同じことがいえるだろう。そこでは作者の個性や身体性、モチーフやコンポジションによって唯一無二の芸術家の思考や感情を表すというよりは、ミシン刺繍にそのまま置き換えることそれ自体が作者のコンセプトとなり、現前のイメージの別の側面を暗示させる。
だが完全なコピーを容易く、無限に生みだす機械的な量産とは異なり、ミシン刺繍はその半分が手仕事である。青山の作品全てに言えることだが、その表面のイメージが刺繍で再現されたということが分かった後に、鑑賞者はその作品の背後にある膨大な制作の時間、技術を獲得した作業の過程、人の手の緻密さに思いを馳せるだろう。それは精巧なミシン刺繍という手段の物質性がイメージに勝る瞬間であり、絵画や彫刻が生むイリュージョンとは別の、テキスタイルや工芸がもつ物質的な強さの表れであろう。こうしてコピーされたイメージは、テキスタイル化によって複製されうるパターンとなることでそのオリジナルが持つイリュージョンをはく奪されるばかりではなく、ミシン刺繍の背後にある膨大な時間と繰り返しに還元されることで変質する。
青森の伝統工芸でもある津軽こぎんの調査から開始されたからであろうか、ACACで滞在制作された作品《Light and Pattern》は、「テキスタイル」あるいは「手工芸」にまつわる問題と直接的に関わっているが、当然のことながらここでもその関心は社会へと向かっている。制作された三つの作品は、ウィリアム・モリスのパターンから借用された植物文様、正六角形を基本とした幾何学文様である麻の葉文様、そしてフランク・ステラの作品のようなストライプ文様が薄いオーガンジーに刺繍された作品である。それらは図も地も白い糸で刺繍されているために光の中ではほとんど真っ白にしか見えない。しかし暗闇ではパターンに用いられた白い蓄光の糸が薄緑色に光り、その表面の文様を淡く浮かび上がらせる(fig.4)。
規則正しい文様は、非個性的で、還元的な形を繰り返すのみであるが、一方でそれぞれのパターンが生まれた時にはそれぞれに意味や祈りにも似た意図があった。だが現在ではそれらの背景は失われつつあり、単なるパターンとして形骸化している。青山はここに今回のプログラムテーマである「storyteller」に対するアプローチとして、「消失するイメージ」「消失する物語」を重ねる。それはテクノロジーの進歩によって変化していく手仕事、伝統工芸あるいはその継承といった近代化で失われてしまうもの、失われる過程に在るものに対する一つの考察でもある。消失するのは過去の技術か、個々の文様か、あるいはある地域ある時代の文化の体系か。一方でこれらのパターンはしばしば境を越えて自由自在に展開し、ある地域の一パターンだと思っていたものが時代や地域を越えた共通性を持ち、世界との結合を可能にする言語となりうる。そう考えると、それらは個々の物語が消失したとしても、形として、その精神として、作業として、姿を変えて存続し完全に消失することはないのだろう。
青山が安易なオリジナリティを否定し、イメージのアプロプリエーションや「機械」という言語を用いて、逆説的に作品によって示しているのは、こうした極限までそぎ落としていったその最後に漏れ出てくる何かである。最後に残るそれは、青山がいうところの「労働」であり「人間の尊厳」[2] であり、芸術というある特殊な分野の問題としてではなく、人類が共有する創造の形とその精神の所在であろう。
会場で流されていたミシンの連続音とそれに重なるミニマルミュージックは、単純な労働の繰り返しを強調する。一方で正面の壁面にはニューズウィーク日本版の記事をただひたすら縫い続けるミシンの手元が映されていた。それぞれの記事の見出しやイメージはショッキングでありながら、ばらばらにされ、無作為に選ばれて縫いつけられていくさまは、ショッキングなイメージが繰り返されることにより無化されることを示したウォーホルの《惨劇》シリーズのイメージの扱い方を想起させる。だが、それらがミシン刺繍によって一本の道のように延々と、淡々と縫い合わせられ、繋がっていく様は、めまぐるしく変化する社会の背後に在り続ける、揺らぎなく、確固とした何かの存在をにおわせる。
また青山の作品にはしばしば陳腐さと聖性、フェイクと本物のような、相反する価値観が浮かび上がる。今回同時に展示された《Roses 6/6》(2011)やマリア像(fig.5)の作品もそうだが、それはモチーフの性質のみならず、ミシン刺繍でアプロプリエートされることにより、しばしばそのキッチュさを強調する。おそらくそれは絵画とテキスタイルの長きにわたるヒエラルキー闘争がその背後にあるだろうが、青山はこれを逆手にとって扱っているようにみえる。一方で緻密な刺繍という作業それ自体が別の聖性をそこに付加する。だからこそ青山はそれを「誰にでもできる」手段というのであろう。それは芸術の価値の所在を一握りの人間の特殊な創造性にではなく、誰もが持つ創造性に問うているのであり、そこには人間の生産活動や人間存在それ自体への根源的な信頼があるようにみえる。
[1] 青山悟レクチャー「技法とその言語」(2012年12月1日)での発言他。
[2] 青山悟へのインタビューでの発言(2012年12月16日)。

《Light and Patterns》
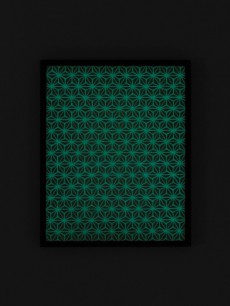
《Light and patterns 1》

《Light and patterns 1》

《Roses 6/6》2011年

《Light and patterns 2》
