この日常のなかでどうやっておちつく場をつくれるか―山麓読書七夜・体験エッセイ
- 日本語
- ENGLISH
3000m級の山々が連なる北アルプスをはじめ四方を山に囲まれた長野県大町市に新幹線とバスを乗り継ぎ到着する。山、ツキノワグマ、温泉、りんご、…検索して出てきたワードから滞在が始まるまでは青森市と近しい土地柄を想像しつついた。実際に大町市に着くと、豊かな自然に包まれているというざっくりとした共通点はあるけれど、青森市で普段見ている八甲田山の倍近くあるように感じられる山脈、そして海と山ではなく密度のある山々に挟まれているという違いが強く印象に残った。今冬の豪雪が夢だったかのように青森で雪の存在を意識することがなくなった7月後半でも、大町市からは猫に引っ掻かれたような白い筋が山々の頂近くに残っているのが見える。商店街のロゴマークやお店の名前、喫茶店に飾られた木彫りのレリーフなど、山の存在は生活の中にも感じられる。ここに暮らす人々にどれほどこの山々は影響を与えてきたのだろうか。(注1)
「山麓読書七夜」はアーティストの内田涼さんと村上慧さんが大町市に移住したことをきっかけに結成した「山麓おちつくおうち計画」による初のレジデンス企画である。企画メンバーは内田さん、村上さんと、北アルプス国際芸術祭実行委員会が主催する「信濃大町アーティスト・イン・レジデンス」に携わっていた関谷花子さん、淺井真至さん、地域おこし協力隊でもある路雨嘉さんの5名で、みなさん大町市を拠点に表現活動を行っている。今回のレジデンスは2025年7月14日(月)から21日(月)の7日間に渡り、昭和46年に建てられた旭町教員住宅の6棟をリノベーションした「あさひAIR」を滞在先として行われた。公募で選ばれた4名の滞在者、栗本凌太郎さん(日記屋月日 店長)、清水里栄さん(作家)、三原聡一郎さん(アーティスト)と執筆者の原田は「いったんおちつこう」と墨書きされた言葉とともに、企画メンバーと地域のみなさんに迎え入れられて滞在をスタートした。
レジデンスの概要やスケジュール、またプログラム中に行われた読書座談会の書き起こしなどは「山麓おちつくおうち計画」のnoteに掲載された「山麓読書七夜2025レポート」にまとめられている。ここではいち参加者として体験したことやそこから考えたことをまとめてみたい。

「いったんおちつこう」を指差す村上慧さん(撮影:小澤貴弘さん)1日目@交流棟
「読書」のレジデンス
“日常生活を送る中で、じっくり本を読む時間を確保するのは意外と難しい。積んだままの本、途中で諦めてしまった本、難しくてひとりでは読み進められない本……。「山麓読書七夜」は、読みたいけれど読めていない、だけど自分にとってきっと大切な本を読むための時間をつくります。それは日々の仕事や生活に追われ、いつしか贅沢なものになってしまった読書体験を自分たちの手に取り戻すための時間でもあります。” (「山麓おちつくおうち計画」のInstagramポストより)
本を読むことは表現に携わる人々にとって大切な行為の一つであるように思う。また、読書は1人で行うことができるパーソナルな行為でもありながら、読書会のように人と人が集うきっかけにもなる。「山麓読書七夜」の公募情報を目にしたのは、展覧会や文化的なイベントが都市と比べると少ない「地方」に暮らすようになり、それゆえに本というメディアが持つ可能性を改めて感じていたタイミングだった。読書という行為がレジデンスの軸になっていること、リサーチや制作を必須としていないこと(むしろ「おちつくこと」が推奨されていた)、1週間という短くもまとまった期間であること、その他にも応募要項に書かれたことに、これまで本や写真を軸に活動してきた身として、また国際芸術センター青森(ACAC)というアーティスト・イン・レジデンス(AIR)を主とする施設で働いている身としても興味を惹かれた。
滞在には「自分で読む本」と「みんなで読む本」の2種類を持っていった。滞在者のみならず企画メンバーも「みんなで読む本」を持ち寄り、それらは交流棟にあった棚に並べられた。朝食を食べたり本を読むために交流棟に訪れると、その棚のレイアウトが変わったり、置いてある本が増えたりもし、他の滞在者や企画メンバーと会わない日でもかれらの存在が感じられる場所になっていた。二、三日いろいろな場所に訪れて試す中で、私は交流棟とあさひAIRの近くにある喫茶店「茶房かじか」を読書スポットとすることにおちついた。それは家ではなく外で読書をする習慣がついているからと思っていたが、それだけでなく私が「自分で読む本」として選んだものは読むための心構えやそのための空間が必要なものだったからだと今では思う。喫茶店では常連客と店主の語らいに耳を傾けながら、交流棟では時折訪れる他の滞在者や企画メンバーと会話を交わしつつ本を読み進めた。この自分が読みたい本を読むことは、自分自身の中で終始するプライベートなものでなく、こうした微細な交流のなかで絶えず自分がいる現実と本との往復がある行為だった。
7日目に行われた座談会では同じ場所・期間でレジデンスをしていた滞在者の中でも、1週間の過ごし方や本への向き合い方が多様であることを知るきっかけになった。滞在者に与えられた部屋の中で集中して読む人や、街のカフェと交流棟や自室を行き来する人。付箋の色を使い分けて章ごとに付箋を貼っている人、付箋を貼った意味を忘れる人や自分に本を読んでいると言い聞かせるために貼っている人。100ページで一区切りとページ数を区切って読み進めていく人。本をもとにノートや読書日記をつける人。そもそも、各自がセレクトした「自分で読む本」も「これまで読めていなかった本」という共通点はあれども各種各様の視点が別々のままあることを示すような存在だった。滞在者同士の関心が別々に、だが時には重なりあいながらも本を読むという共通の行為でつながりが生まれたのは面白い。普段行っている活動も関心もさまざまであるのに、また、おそらく一般的なレジデンスでは揃わないような面々が今回集えたのも、この「山麓読書七夜」ならではだと思う。
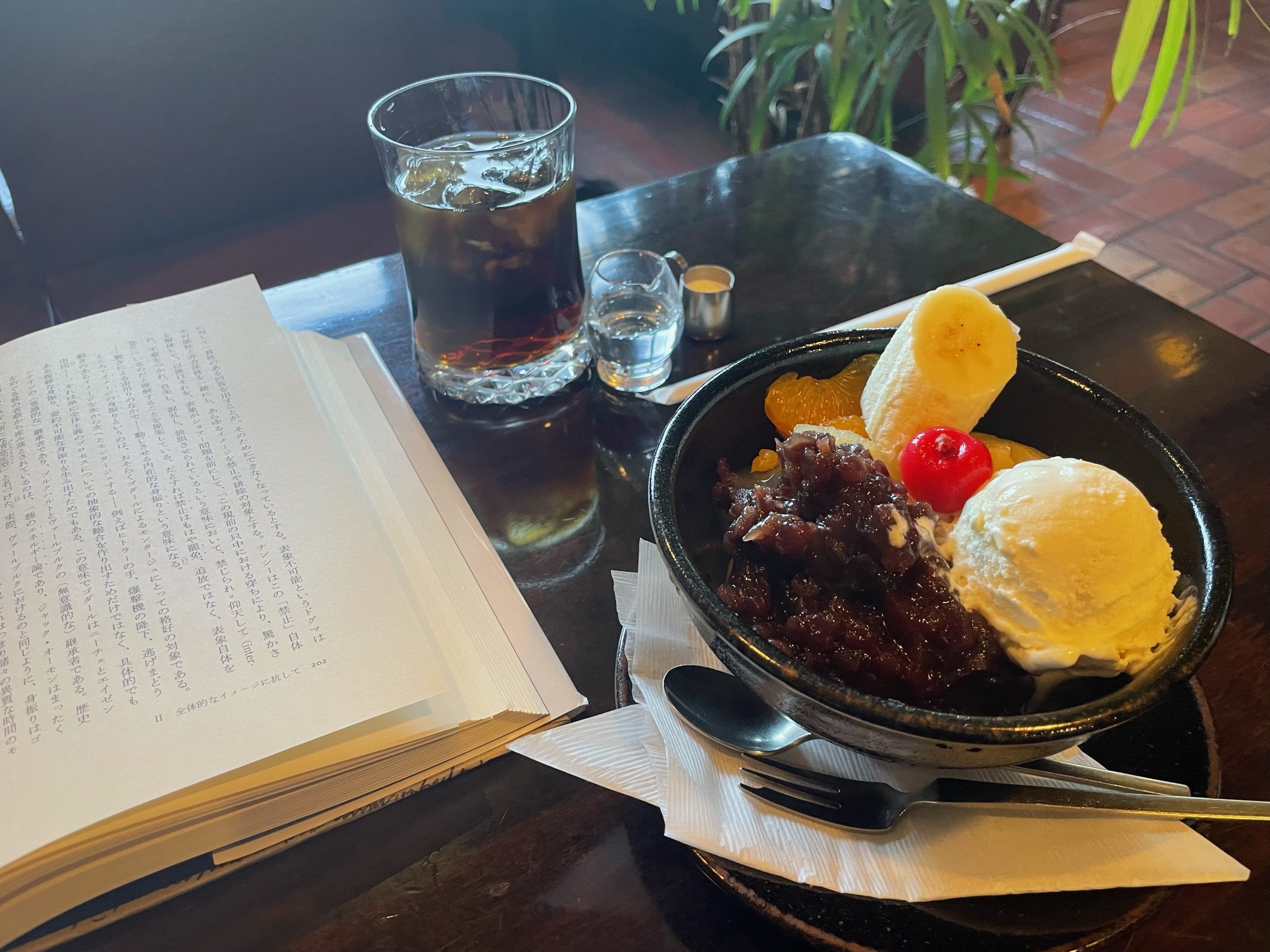
自家製小倉餡のクリームあんみつとアイスコーヒーと最後の読書 7日目@茶房かじか
文化的な活動を続けること
レジデンスでは受け入れる側が滞在者の興味関心やリサーチ・制作内容に合わせてさまざまな場所に連れていくことがある。現にACACがそうだ。しかし、今回のレジデンスの軸はあくまで「読書」であり「おちつく」ことを大切にした企画である。そうしたテーマから企画メンバーは他の場所に滞在者を連れ出して良いものか、どれほどの頻度だと適切か、滞在者それぞれの様子を見守りながら手探りで行っていた(注2)。大町市は商店街やスーパーなどがあさひAIRの近くにあり生活するには徒歩や自転車で事足りるが、山やダムや湖に行こうと思うと車移動の方が格段に便利だ。個人的には初めての場所に来たらその土地のさまざまなものを見たいし、そこに住んでいる人たちのお気に入りの場所にも行きたくなる。しかし、日常ではなかなか得ることができない自分のための読書をすることを担保された期間でもある。滞在者も企画メンバーもお互いに手探りでこのレジデンスの場を保つように考えながら行動を共にしたり、1人になって読書をしたりした。
公募型のレジデンスはACACで実施しているものも含め、限られた滞在期間に作品制作やリサーチの成果を展覧会やイベントなどの形で発表することが求められる場合が多い。ACACは青森に暮らす人々とアート・文化を繋げるという公のアートセンターの責任もあり成果発表を必須として公募AIRを行ってきた。だがそれらは、まとまった予算やサポートするスタッフがいて成り立つものである。企画メンバーの村上さんが初日や座談会で触れていた、既存のレジデンスでは行うことができない文化的に意味のあることを行いたいという姿勢や、内田さんが座談会で話していた仕事としてではなく自分自身の制作とのバランスをとりながら続けていく形を模索していることは滞在中も滞在を終えてからも心に残っている。おそらくそれはオルタナティブなAIRである「山麓読書七夜」の核だったのではないかと思う。
昨年のACACの公募AIRを振り返ると、カタログの冒頭で自分が寄せた言葉のなかに滞在アーティスト同士が生活の中で交流している様子やそこから学び合っている様子に、AIRならでは可能性を感じていたことを思い出した。限られた時間の中でリサーチや制作、発表、記録化をこなさなければならない滞在者と受け入れ側の緊張感や労力は、私自身がこの一年あまり行なってきたことなのである程度想像ができる。こうしたその都度アウトプットを行う方法は村上さんが言うように(注3)、社会の枠組みに沿って決められた時間のなかで行う仕事としての側面を持つようにも思われる。そして、本当に自分自身がやるべきことを突き詰めて形にするには数年やときには数十年単位の時間がかかるものが多くあるはずだ。ACACのレジデンスがその膨大な月日の数週間や数ヶ月になればこれほど嬉しいものはないように思う。「山麓読書七夜」に参加した経験は、公的なアートセンターで働く職員としての身の置き方やAIR事業の進め方を考える機会となった。

湖の水温を触れて確認する(撮影:淺井真至さん)4日目@木崎湖
普段は日記を書かないけれども、初日に栗本さんや村上さんの日記についてのお話を聞き滞在中は日記をつけていた。書きなれていないため、日記には忘れたくないことを次の日に思い出してメモのように記していくことにした。7月17日、みなさんと手打ちそばの山品と仁科三湖と街並商店へ訪れた日、7月18日、夜に交流棟でBBQをした日、7月19日、温泉後に村上さんと内田さんのアトリエに訪れた日は特に書いている量が多く、ほとんどが交わした会話の内容やそこから感じたことを思い出して書いていた。本は手元にある限り読み返すことができるが、人との出会いや交流は同じことを繰り返すことは不可能だ。真至さんの不思議だけど的を射ているような行動と思考、花子さんの冷静さと密やかな温かいサポート、涼さんの人と対等に向き合う視線、村上さんのゆるやかにある熱い思い。路雨嘉さんが描いた山岳マップはこの土地への惜しみない気持ちで溢れていた。そうした人々と他の参加者のみなさん、今回出会えた方々と交わした言葉の数々や行動を共にしたことは忘れたくない。
いつかまたあの人たちがいるあの光景に出合いたいな、と思う。
原田桃望(国際芸術センター青森・学芸員)
注1…大町市にある「大町山岳博物館」はそうした山と人との関わりについて常設展で取り扱っている他、北アルプスのなりたちや山の生き物について知ることができる場所である。実際に高山動物も飼育されており、私が訪れたときは夏毛のライチョウを見ることができた。
注2…「山麓読書七夜2025レポート」にまとめられた座談会でも企画メンバーがこのことについて触れている。
注3…「山麓読書七夜2025レポート」にまとめられた座談会の後半で村上さんが話していること。